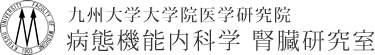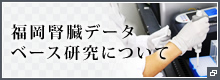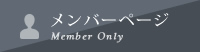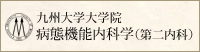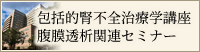学会・研究会2018.08.03
移植腎病理研究会第22回学術集会が開催されました.
2018年7月21日に移植腎病理研究会第22回学術集会が開催され,当研究室の松隈先生(H20)が0時間生検を用いた研究を発表しました.

Banff分類2017に改訂されて初めての移植腎病理研究会であり,Chronic active TCMRの病態に関して注目が集まりました.tiとi-IF/TAを基準とした診断は移植腎予後に関連すると報告されていますが,拒絶の診断としての特異性としては問題があり,全国の移植腎病理医の頭を悩ませているのが実情のようです.
これまで腎移植患者さんは移植外科医の先生方が診察することの多い分野でありましたが,多数の免疫抑制薬の調整が必要であることや,プロトコール腎生検による腎炎の発症・進展の瞬間を目の当たりにできることから,腎臓内科医にとっても学ぶべき魅力が溢れており,積極的に関わっていくべき分野と考えられます.
次回の移植腎病理研究会は当研究室の升谷先生(H6, 現福岡大学 腎臓・膠原病内科学)が主催で開催されますので,ますます盛り上がることが期待されます!

Banff分類2017に改訂されて初めての移植腎病理研究会であり,Chronic active TCMRの病態に関して注目が集まりました.tiとi-IF/TAを基準とした診断は移植腎予後に関連すると報告されていますが,拒絶の診断としての特異性としては問題があり,全国の移植腎病理医の頭を悩ませているのが実情のようです.
これまで腎移植患者さんは移植外科医の先生方が診察することの多い分野でありましたが,多数の免疫抑制薬の調整が必要であることや,プロトコール腎生検による腎炎の発症・進展の瞬間を目の当たりにできることから,腎臓内科医にとっても学ぶべき魅力が溢れており,積極的に関わっていくべき分野と考えられます.
次回の移植腎病理研究会は当研究室の升谷先生(H6, 現福岡大学 腎臓・膠原病内科学)が主催で開催されますので,ますます盛り上がることが期待されます!